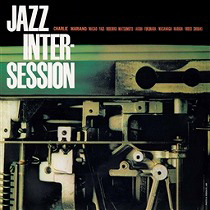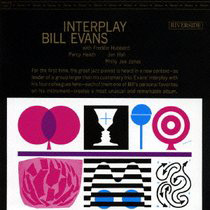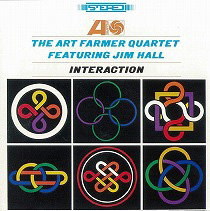映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦
第45回 60年代日本映画からジャズを聴く その6 八木正生におけるジャズと映画の葛藤
第45回 60年代日本映画からジャズを聴く その6 八木正生におけるジャズと映画の葛藤
アルバム「ジャズ・インター・セッション」とインタープレイ
本コラム第41回で八木正生作曲の「ジンク」が収録されたコンピレーション盤「キング・オブ・JPジャズ ドゥー・ステップ」を紹介している。この度、その「ジンク」が初めて八木によって演奏されたオリジナル・アルバム「ジャズ・インター・セッション」(キング)が初CD化されてしまった。欣喜雀躍とはまさにこのこと。ついでにもう一枚、今回のCD化シリーズ「キング・ヴィンテージ・ジャズ‐コレクターズ・エディション」から一タイトル上げておく。「ラテン・バロック・コレクション」(キング)である。こちらも八木がピアニストとして参加している。帯に「ジャズとラテンとクラシックを結びつけた問題作」とあることからわかるように全十曲ヨハン・セバスチャン・バッハの楽曲。それをジャズにアレンジした企画物である。残念ながらアレンジャーのクレジットは記載がないのだが、八木と前田憲男が担当したのではないかと推察出来る。前者は1964年、後者は65年のリリース。さて「ジャズ・インター・セッション」のジャケットを見ても八木がアルバム・リーダーであることはわからない。参加メンバーの文字の大きさで比較するとチャーリー・マリアーノだけが微妙に大きいから彼がリーダーのように見えてしまうが、これは彼が著名な外国人演奏家だからだろう。ゲスト・ミュージシャンと言ってもいい。
アルバムのコンセプトはライナーノーツを読むことで明らかになる。引用し始めると無駄に長くなりそうなので、手短に紹介しよう。これはその当時ジャズの世界で話題となっていた「モダン・ジャズにおけるインタープレイ」という方法論を、八木をリーダーとすることで実践してみせたアルバムである。「インタープレイとは何ぞや」、という方向に今回のコラムを持っていくといつまでも本題に入れないからこれまた手短に。ソロイスト(アドリブ演奏者)とアカンパニスト(伴奏者)の、悪く言えば「主従的な関係」を放棄し、ソロイストに対してアカンパニストが積極的にアドリブで介入する、対等なやり方のことだ。これだけではかえって分かりにくい気もするが、現在のモダン・ジャズ演奏の主流は必然こういったものだと思う。だから方法論というよりも、もっと、今日のジャズメンには血肉化された心構えとかスタンスみたいな感じもあるね。ちなみにライナーにはこうした方法によるアルバムとしてビル・エヴァンス(ピアノ)とジム・ホール(ギター)のデュオ「アンダーカレント」“Undercurrent”(United Artists)と「インタープレイ」“Interplay”(Riverside)、そしてジム・ホールがアート・ファーマー(トランペット)と双頭カルテットを結成した「インターアクション」“Interaction”(Atlantic)が挙げられている。「インター」というのは「相互的」という意味だ。互いに演奏で互いを触発するという性格がおのずから見えてくると思う。そして多分この頃、こういった概念というか手法というか心構えが業界的にもファンサイドでも一種の流行語になっていたのだと思う。本コラム第24回でもエヴァンスとホールについては述べている。
また第25回ではエヴァンスとベーシスト、スコット・ラファロに関して語った。興味のある方は読みなおしておいて下さい。インタープレイという概念によってその演奏の方法が語られることの多いのは、やはりエヴァンスとラファロとポール・モチアン(ドラムス)のトリオだからだ。彼等が残した「インタープレイ満載の」アルバムの中でも、アルバム自体の出来というよりむしろ貴重な歴史的なドキュメントとして、現在では「ザ・コンプリート・ライヴ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード1961」“The Complete Live at the Village Vanguard 1961”(Riverside)というCDを聴くことが出来る。この日のライヴは既に二枚のアルバムとして残されているのだが、この三枚組CDはさらにそこに、この1961年6月25日のライヴの未発表演奏や曲間の会話なども加えて全録音を時系列に沿って集大成している。モチアンも証言しているように全部で五セットの長丁場だったことがわかる。午後から始まり深夜二時までやっていたそうだ。
十一日後には事故死してしまうラファロ最後の演奏が捉えられていることで、この日のライヴを収めたアルバム「サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード」“Sunday at the Village Vanguard”(Riverside)と「ワルツ・フォー・デビー」“Waltz for Debby”(Riverside)は変ることない名盤の位置を占めているけれども、いっぺんこのコンプリート盤も聴いてみることをお勧めしたい。と言うのは、本来なら削られてしかるべき音源を一緒にまとめて聴くと結構だらだらやっているのが分かって親しみが湧くのだ。昔からこのライヴが聴ける二枚のアルバムは、お客さんが演奏を聴いていないことで有名なものだが、この完全盤を聴くとその感じはさらに深い。中山康樹が現場にいたら思わず「エヴァンスを聴け!」と怒鳴ってしまったに違いない(心の中でね)。