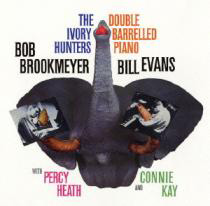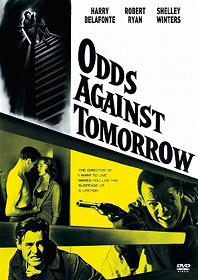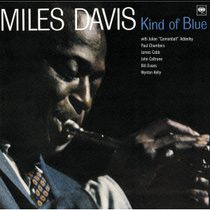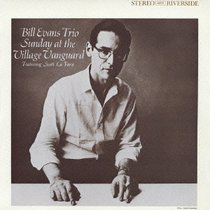映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦 第24回 『拳銃の報酬』セッションその後 その1
ビル・エヴァンス
今回取り上げるのは『大運河』成功の「余波」で、ついにルイスがアメリカ映画に進出して『拳銃の報酬』を画期的なジャズ音源映画に仕上げた、その「さらなる余波」のこと。MJQはルイスのピアノ、ミルト・ジャクソンのヴァイブラフォン、パーシー・ヒースのベース、コニー・ケイ(別に女ではない)のドラムスからなるが、『拳銃の報酬』でルイスは(1)ピアノを弾かず、(2)作曲・編曲に専念し22名から成る大型オーケストラを率いた。サントラ音源録音のために持たれた『拳銃の報酬』セッションは、この二つの件に起因してその後のジャズにささやかながら不可逆的な影響を及ぼすことになる。
問題の映画『拳銃の報酬』サントラ盤が録音されたのは1959年7月16、17、20日の三日間である。近年CD化された音源は全19曲にものぼるが、もちろんそれぞれの楽曲は短く、ジャズとして特筆すべき成果にも乏しい。従ってまず記しておくべきなのは、ここから派生した「本家MJQ」のアルバム「明日に賭ける」“Odds Against Tomorrow”(レーベルATLANTIC)の方だろうか。19曲から「スケーティング・イン・セントラル・パーク」「ノー・ハピネス・フォー・スレイター」「ア・ソーシャル・コール」「キュー♯9」「ア・コールド・ウィンド・イズ・ブローイング」「オッズ・アゲンスト・トゥモロー」の6曲をチョイスして本来のMJQが再録音したもの。録音日は1959年10月9日である。以後、人気レパートリーとなる「スケーティング・イン・セントラル・パーク」“Skating in Central Park”のMJQによる初演となる。近年このアルバムは「映画におけるMJQ」“The MJQ in the Movies”(レーベルGIANT STEPS RECORDINGS)のタイトルで『大運河』『コーヒー・アンド・シガレッツ』(ジム・ジャームッシュ監督)の音源と合わせてCDリリースされた。単独ではCD化されていない。
今回はまず(1)の件からテーマにしよう。『拳銃の報酬』セッションでは、ルイスがピアノを弾かなかったために新たにピアニストが必要になった。そこで呼ばれたのがジャズ史上最高のピアニストの一人ビル・エヴァンスであった。何故わざわざエヴァンスが、と考えても特に意味はない。しかしその結果、このセッションでの「スケーティング」には歴史上ただ一度エヴァンス、ジャクソン、ヒース、ケイという変則MJQが出現したわけで、まさしく「VSOP」(ヴェリー・スペシャル・ワンタイム・パフォーマンス)状態。
さて、この1959年という年はジャズ史的には特別な年と言える。理由その一。3月2日と4月22日にマイルス・デイヴィスの「カインド・オブ・ブルー」“Kind of Blue”(レーベルCOLUMBIA)が録音されているのである。ここで音楽監督的な役割をし、もちろんピアノも弾いているのがエヴァンスだ。このアルバムは50年代中盤以降、バップに替わるジャズの演奏様式として「モード手法」を追究してきたマイルスが、エヴァンスというブレーン、力強い味方を得て放ったモダン・ジャズ史上の金字塔と呼べる。
その一方、「カインド・オブ・ブルー」の最初の録音から十日後、3月12日にはヴァルヴ・トロンボーン奏者ボブ・ブルックマイヤーのアルバム「アイヴォリー・ハンターズ」“The Ivory Hunters”(レーベルUNITED ARTISTS)にリズム陣の一人として参加している。この際のベースがヒース、ドラムスがケイ、即ちMJQの二人だ。もっともここでブルックマイヤーはトロンボーンを吹かず余技のピアノだけを弾いており、従ってエヴァンスとの「二人ピアノ」が(現在から見ると)有り難くもないセールス・ポイントとなってしまった。珍品というかほとんど企画物、とでもいうべきコンセプト。
さらに、その二週間後の3月25日には作曲家・編曲家ジョージ・ラッセルのジャズ・オーケストラ作品「ニュー・ヨーク、N.Y.」“NewYork, N.Y.”(レーベルDECCA)中の「イーストサイド・メドレー」にピアノのソロイストとしてフィーチャーされてもいる。エヴァンスにはこの時点で既に二枚のリーダー・アルバムがあったとはいうものの、こうした上記三枚から判断すれば「売れっ子サイドメン」としてのスタンスがメイン・ワークであったのは明白だ。いや、正確に述べればこの三枚はそうした中の最上のものであり、実際にはここまででその十倍以上にも及ぶ録音機会に一サイドメンとして演奏参加しているのである。それらが気鋭のピアニストに絶好の研鑽の機会を与えたのは確かだとしても、同時にそれが麻薬代を稼ぐための一時しのぎであったのも事実。
そうした次第で59年7月『拳銃の報酬』録音が、エヴァンスにとって雇われ仕事以上のものでなかっただろうとは容易に推測されるのだ。変則MJQの音楽も形式的なものに過ぎず、それほどの聴きものにはなっていない。エヴァンスの全キャリアを見る上で「カインド・オブ・ブルー」に並んで重要なセッションは、やはりこの59年、年末12月28日に催されたスタジオ録音に尽きる。ビル・エヴァンス・トリオ「ポートレイト・イン・ジャズ」“Portrait in Jazz”(レーベルRIVERSIDE)としてリリースされるものである。59年がジャズ史上特別な年である理由その二がこれだ。史上最も有名なトリオ結成による快進撃はここから始まる。
トリオはエヴァンスのピアノにスコット・ラファロのベース、ポール・モチアンのドラムスから成り、画期的なのは三者が音楽的に対等の関係にある点だ。ピアノが主役でメロディを担当、ベースとドラムスが伴奏する、という従来の静的な図式を逸脱し、ベースやドラムスが、エヴァンスのピアノに絡み合うように、異なるメロディやズレたリズムを強調して演奏を推進していく。こうしたやり方は「インタープレイ」と呼ばれ、エヴァンスは後年、同名のアルバム“Interplay”(レーベルRIVERSIDE)もリリースしている。
「ポートレイト・イン・ジャズ」は公式的にはエヴァンス三枚目のリーダー・アルバムになるが、この伝説的トリオは以後「エクスプロレイションズ」“Explorations”「サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード」“Sunday at the Village Vanguard”「ワルツ・フォー・デビイ」“Waltz for Debby”(いずれもRIVERSIDE)わずか三枚のアルバムだけを残して消滅してしまう(ブートレグ、後発再編集物は除く)。1961年7月6日、スコット・ラファロが交通事故死したからである。実質の活動期はわずか一年半だった。ここからエヴァンスは深刻なスランプに陥り、リーダー作が途絶えるのはもちろんのことサイドメンとしての録音も急激に減少してしまう。
その彼がようやく立ち直るのが62年4、5月の「アンダーカレント」“Undercurrent”(レーベルUNITED ARTISTS)録音からであった。これはギタリスト、ジム・ホールのアルバムに請われてエヴァンスが参加した完全なデュオ(二重奏)。当時としては比較的珍しい形式だが、実はホールとエヴァンスは以前二回だけ共演している。その一つが『拳銃の報酬』セッションだったのである(もう一回の録音は後述)。
ジャズ評論家、中山康樹によればエヴァンスがスランプから脱したのは二回目の「アンダーカレント」セッション即ち5月14日の録音だったとされる。最初の4月24日のセッションからは結局「アイ・ヒアー・ア・ラプソディー」一曲を除き全てボツとなっているからだ。もっとも、このテイクは一応水準を超えたと判断されたからこそレコード化されたわけで、それほど悪い出来ではない。エヴァンスの生涯で最も悪い出来の演奏はこれをさかのぼること二十日前、4月4日のソロピアノ録音四曲である。当時はいずれも当然ボツとなったものだ。とりわけ、チャーリー・パーカーの46年6月9日録音「ラヴァー・マン」にも比べられる(連載第二十二回参照)珍演として後年有名になったのが「ダニー・ボーイ」“Danny Boy”で、現在このテイクは「イージー・トゥ・ラヴ~ビル・エヴァンス・ソロ」“Easy to Love”(レーベルRIVERSIDE)で容易に聴くことが出来る。
さすがに麻薬やアルコールの酩酊状態であったということはないはずだが、やはり結局やる気になれなかったのか、とにかくどこに向かっていくのか全くわからないソロが10分にもわたって繰り広げられるのはある意味圧巻(もっともこれ実は、半分「指慣らし」のつもりだったのではないか、という説もある)。終わるかと思ったところからまた始まってしまう展開から鑑みると、多分、本人自身何か納得のいかないものを感じていたはずだ。ともあれ、そうした演奏から一カ月余の後、二回目の「アンダーカレント」セッションで試みられた一曲が『拳銃の報酬』からの挿入曲「スケーティング・イン・セントラル・パーク」のデュオ版であった。
自分一人で全てを解決しないといけないソロピアノに比べれば、二人での演奏には互いへの信頼とそれ故の拘束が当然生まれることになる。特に、ピアノとギターはどちらも単独でメロディと和音を奏でられる楽器なのでデュオはかえって難しいと言われる。最初のセッションが思うような成果を上げられなかったのも、そこに原因があったのかも知れない。二度目のセッションで取り上げた「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」“My Funny Valentine”がジャズにおけるギター&ピアノ・デュオのお手本とされるのはそれを克服したが故であり、二つの楽器が互いにメロディとリズムを補い合ったり、逆に互いを追いかけたりする仕掛けがスリリングそのもの。これはまさにインタープレイの極致と呼べる。この演奏を、前記中山は「ポートレイト・イン・ジャズ」における「枯葉」“Autumn Leaves”の等価と見なしている。だとすれば彼がスランプを脱したのはいわば音楽的ショック療法のようなものだったに違いない。通常スローなテンポで演奏されるスタンダード・ナンバーをここでエヴァンスとホールは過激なまでの高速調でプレイする。そしてそれを通過儀礼のようにしてその後二人は「スケーティング・イン・セントラル・パーク」を静謐に仕上げている。
MJQと異なり、ここでの決定的名演をただ一度残して、以降エヴァンスはこの曲をレコーディングすることはなかった。(以下次回へ続く)