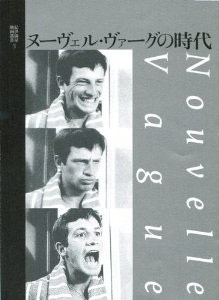海外版DVDを見てみた 第5回『メイズルズ兄弟を見てみた』 Text by 吉田広明
アルバートとデイヴィッドのメイズルズ兄弟はアメリカのダイレクト・シネマの代表的映画作家。兄がカメラを、弟が録音を担当し、二人で撮影するスタイルで映画製作をしてきたが、デイヴィッドが87年に死去してからは、旧作のフッテージを編集したもの以外、二人での監督クレジット作はない。アルバートは現在もカメラマンとして活躍しているようだ。二人による映画は、有名人に密着して、その人となりを捉える、というものが多いが、それも、二人だけという身軽な撮影体制と、二人の温厚な人柄(といっても写真で見る限り、ないし、映画に映り込んでいる彼らの様子から判断してのことに過ぎないが)があって可能になっているものだろう。彼らの作品は十数本あるのだが、ここでは代表作と言える数本の作品を見てみた。
あるインタビューでアルバート・メイズルズは、映画作りに関して一番重要なことは、「他の人や場所について、信頼に値する情報や知識を得ること」、と述べている。「信頼に値するreliable」ということが大事なわけだが、ダイレクト・シネマはそれを、作り手の意見や見解によって偏向を受けていない、と解する。そうした偏向は、実際の映画においては、例えばナレーションや、ある種の感情を惹き起すための音楽、として現れる。無論ドキュメンタリーには、混沌とした現実に理路をつける、という役割もあるし、作り手が強く主義主張を訴え、現実にコミットするという役割もある。そのために観客を導く場合もあるだろうし、その際ナレーションや音楽は有効だろう。しかし、ダイレクト・シネマはその道を採らない。あくまで現実の混沌を混沌として差し出し、あるいはそこで迷うことをすら観客に引き受けさせようとする。例えば(詳しくは後述するが)ローリング・ストーンズのフリー・コンサートを撮った『ギミー・シェルター』(70)では、コンサートの混乱が混乱のまま収められており、とっさには何が起こっているのかすら分からない。しかし現実の混沌、訳の判らなさをそれ自体として体験することも映画なのだ、とメイズルズは考える。ダイレクト・シネマは「客観性」を重視するにしても、それは現実に対して高みから見物するという悠長な態度を観客に許すものではない。むしろ、現実の中に入り込み、そこで途方に暮れ、自分で方向性を見つけ出し、迷いながらも手探りで進むことを強いる過酷なものだ。アルバートは、エンターテインメントの定義には一、「気晴らし」と二、「engagement」(訳をつけるのが難しい、実存主義における「アンガージュマン」のことと思っていいだろう)があるとして、後者が一番いい定義だと思うと述べているが、ダイレクト・シネマにとって映画とは、「engage」することなのだ。
ダイレクト・シネマ
ダイレクト・シネマは、50年代後半にカナダのケベックで、カナダ国立映画製作庁によって製作された映画に始まるとされる新たなドキュメンタリーの傾向で、その特徴はまず何より、手持ちカメラによる撮影と同時録音と、ナレーションの不在である。シネマ・ヴェリテと同義とされることもあるが、シネマ・ヴェリテには、撮影対象を挑発するなどして撮影行為そのものを観る者に意識させ、ドキュメンタリーの「自発性」「客観性」に常に疑問符を突きつける(そのアメリカにおける典型的な例を、前回のシャーリー・クラークに見た)傾向があることを考えると、やはり微妙にずれるものと思っておいた方がいいように思う。ただし、ダイレクト・シネマのような、限りなく素のままの現実を切り取る、という意識(とそれを可能にする技術)をもって作られる映画が現れたからこそ、本当に「客観的」な映画などありうるのか、という疑義も現れたのであって、ダイレクト・シネマとシネマ・ヴェリテが相関関係にあることは確かである。50年代後半から60年代にかけて世界的に起こった新たな映画の運動、その中でダイレクト・シネマの占める位置については、『紀伊國屋映画叢書2 ヌーヴェル・ヴァーグの時代』を参照してもらいたいが、ここではメイズルズ自身の発言からダイレクト・シネマ観を見てみよう。あるインタビューでアルバート・メイズルズは、映画作りに関して一番重要なことは、「他の人や場所について、信頼に値する情報や知識を得ること」、と述べている。「信頼に値するreliable」ということが大事なわけだが、ダイレクト・シネマはそれを、作り手の意見や見解によって偏向を受けていない、と解する。そうした偏向は、実際の映画においては、例えばナレーションや、ある種の感情を惹き起すための音楽、として現れる。無論ドキュメンタリーには、混沌とした現実に理路をつける、という役割もあるし、作り手が強く主義主張を訴え、現実にコミットするという役割もある。そのために観客を導く場合もあるだろうし、その際ナレーションや音楽は有効だろう。しかし、ダイレクト・シネマはその道を採らない。あくまで現実の混沌を混沌として差し出し、あるいはそこで迷うことをすら観客に引き受けさせようとする。例えば(詳しくは後述するが)ローリング・ストーンズのフリー・コンサートを撮った『ギミー・シェルター』(70)では、コンサートの混乱が混乱のまま収められており、とっさには何が起こっているのかすら分からない。しかし現実の混沌、訳の判らなさをそれ自体として体験することも映画なのだ、とメイズルズは考える。ダイレクト・シネマは「客観性」を重視するにしても、それは現実に対して高みから見物するという悠長な態度を観客に許すものではない。むしろ、現実の中に入り込み、そこで途方に暮れ、自分で方向性を見つけ出し、迷いながらも手探りで進むことを強いる過酷なものだ。アルバートは、エンターテインメントの定義には一、「気晴らし」と二、「engagement」(訳をつけるのが難しい、実存主義における「アンガージュマン」のことと思っていいだろう)があるとして、後者が一番いい定義だと思うと述べているが、ダイレクト・シネマにとって映画とは、「engage」することなのだ。