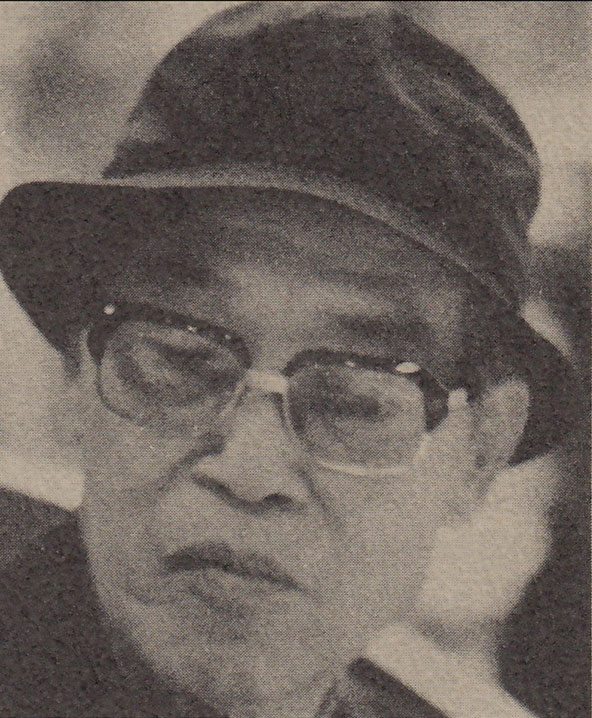コラム 『日本映画の玉(ギョク)』Jフィルム・ノワール覚書⑤『蜘蛛の街』の登場 Text by 木全公彦
今回は『蜘蛛の街』を取り上げる。監督は鈴木英夫。のちに主として東宝でスリラー/サスペンス映画に真価を発揮した監督である。『蜘蛛の街』は監督第2作で、彼が手がけた最初のスリラー/サスペンス映画になる。
下山事件では、死体発見の前日から死亡推定時間までの空白の失踪時間に、下山総裁らしき人物の目撃証人が多数あり、それが事件の鍵となる重大な証言になったが、その目撃情報が謀殺を撹乱するでっちあげだったらどうかという仮説から、倉谷による『蜘蛛の街』のアイデアが生まれた。そのアイデアをもとに、高岩は無辜の庶民が殺された男そっくりの風貌であることをギャング団に利用され、殺人事件に巻き込まれるというスリラー映画の脚本を書き上げる。
高岩は1935年、松竹に入社し、本社の営業部検閲課で働いたあと、1938年には新興キネマに移籍し、六車脩大泉撮影所所長の秘書として働いた。その後1939年に脚本家に転身したという経歴を持つ。戦前から都会の知的若者に人気のあった雑誌「新青年」に掲載された探偵小説を愛読していたという(「にっぽん脚本家クロニクル」、桂千穂編・著、ワールドマガジン社、1996年)。その志向は、戦後第1作となった『夜光る顔』(1946年、久松静児監督)を皮切りにした久松静児監督とのコンビで作られたいくつかのスリラー仕立ての探偵映画に生かされることになる。続く第2作は江戸川乱歩の「心理試験」を映画化した『パレットナイフの殺人』(1946年、久松静児監督)。以降、横溝正史(『蝶々失踪事件』1947年)、木々高太郎(『三面鏡の恐怖』1948年)、角田喜久雄(『虹男』1949年、牛原虚彦監督)、江戸川乱歩(『氷柱の美女』1950年)らの探偵小説を続々と脚色・映画化する(『虹男』以外久松静児監督)。ここからでも分かるように高岩は、いわゆる大映スリラー映画を一手に引き受けてきた脚本家である。『蜘蛛の街』はその高岩が書いたリアリズムを基調にした最初の本格的なスリラー映画だった。プロデューサーは宣伝部長から転じた三浦信夫。低予算で製作することが決まり、監督には新人監督を抜擢することになった。実績のある高岩は、新人・鈴木英夫を監督に指名する。
当時、鈴木はデビュー作『二人で見る星』(1947年)が大映の上層部に不評で、約2年間干されていた。この鈴木自身によるオリジナル脚本は、終戦直後という当時の世相を背景に、戦地から恋人の帰還を待つ女と、ふと出会った帰還兵が次第に心を通わせていく物語だったが、大映が望んだであろうメロドラマ調の演出をあえて避けたところが上層部の不興を買ったのかもしれず、今見ると、干されるほどの悪い出来だとは思えない。ただし、全体に誠実な演出であるが、回想場面でオフボイスでの一人称視点を採用したり、ふいにキャメラを傾けたりと、デビュー作にありがちな野心ばかりが空転している箇所も散見され、積極的に擁護できるような出来ではない。
しかし高岩が『蜘蛛の街』の監督に鈴木を推薦したのは、鈴木が以前にシナリオ・コンクールに応募したシナリオを高く評価し、大映の前身である新興キネマ大泉撮影所に入社するきっかけを与えたのが高岩であったからだった。そればかりでない。高岩は、その後も鈴木が助監督のかたわら、シナリオをせっせと書き、そのうちのひとつ、舟橋聖一の短篇小説を脚色した『母代』(1941年、田中重雄監督)が入社1年目で映画化されたこともある鈴木を脚本の書ける監督として認め、鈴木の秘めたる能力を高く評価していたのだ。
プロデューサー三浦信夫は、第三次東宝争議が時間外手当の扱いをめぐって勃発したことを踏まえて、この作品をいかに低予算でもおもしろい映画を作れることの証明として、ロケーションを多用し隠し撮りも採用したセミ・ドキュのスタイルで撮影し、ギャランティのあまり高くないスターバリューのない俳優を起用し、事前に綿密なコンテと香盤表を作るという、合理的な撮影方式で製作費を切りつめて映画を成立させることにした(最終的にかかった直接製作費は破格の780万円だった)(「読売新聞」1950年6月10日付朝刊)。長い冷飯生活から突然監督に指名された鈴木英夫にとっても監督第2作、もう失敗は許されず、この一作にすべてがかかっていた。
ヒントは下山事件
『蜘蛛の街』は大映脚本部に籍のあった倉谷勇(のちテレビ昼メロの先達監督となる)の原案をもとに、高岩肇がオリジナル脚本を執筆した。倉谷の原案は、連合軍統治下の1949年7月6日早朝に国鉄総裁の下山定則の轢死体が発見された、世に言う下山事件にヒントを得ている。事件は、発覚直後から自殺説・他殺説が入り乱れ、占領下の日本で起きた怪事件のひとつとして、さまざまな仮説をもとに、現在にいたるまで多くのノンフィクション・ノヴェルや映像作品になってきた。1954年に日活で製作された『黒い潮』(山村聰監督)は、自殺説を主張する毎日新聞の記者を描く群像劇。他方、1981年に俳優座映画放送と松竹が共同製作した『日本の熱い日 謀殺・下山事件』(熊井啓監督)は、謀殺説を主張した朝日新聞社の矢田喜美雄記者の著作「謀殺・下山事件」を映画化したもの。下山事件では、死体発見の前日から死亡推定時間までの空白の失踪時間に、下山総裁らしき人物の目撃証人が多数あり、それが事件の鍵となる重大な証言になったが、その目撃情報が謀殺を撹乱するでっちあげだったらどうかという仮説から、倉谷による『蜘蛛の街』のアイデアが生まれた。そのアイデアをもとに、高岩は無辜の庶民が殺された男そっくりの風貌であることをギャング団に利用され、殺人事件に巻き込まれるというスリラー映画の脚本を書き上げる。
高岩は1935年、松竹に入社し、本社の営業部検閲課で働いたあと、1938年には新興キネマに移籍し、六車脩大泉撮影所所長の秘書として働いた。その後1939年に脚本家に転身したという経歴を持つ。戦前から都会の知的若者に人気のあった雑誌「新青年」に掲載された探偵小説を愛読していたという(「にっぽん脚本家クロニクル」、桂千穂編・著、ワールドマガジン社、1996年)。その志向は、戦後第1作となった『夜光る顔』(1946年、久松静児監督)を皮切りにした久松静児監督とのコンビで作られたいくつかのスリラー仕立ての探偵映画に生かされることになる。続く第2作は江戸川乱歩の「心理試験」を映画化した『パレットナイフの殺人』(1946年、久松静児監督)。以降、横溝正史(『蝶々失踪事件』1947年)、木々高太郎(『三面鏡の恐怖』1948年)、角田喜久雄(『虹男』1949年、牛原虚彦監督)、江戸川乱歩(『氷柱の美女』1950年)らの探偵小説を続々と脚色・映画化する(『虹男』以外久松静児監督)。ここからでも分かるように高岩は、いわゆる大映スリラー映画を一手に引き受けてきた脚本家である。『蜘蛛の街』はその高岩が書いたリアリズムを基調にした最初の本格的なスリラー映画だった。プロデューサーは宣伝部長から転じた三浦信夫。低予算で製作することが決まり、監督には新人監督を抜擢することになった。実績のある高岩は、新人・鈴木英夫を監督に指名する。
当時、鈴木はデビュー作『二人で見る星』(1947年)が大映の上層部に不評で、約2年間干されていた。この鈴木自身によるオリジナル脚本は、終戦直後という当時の世相を背景に、戦地から恋人の帰還を待つ女と、ふと出会った帰還兵が次第に心を通わせていく物語だったが、大映が望んだであろうメロドラマ調の演出をあえて避けたところが上層部の不興を買ったのかもしれず、今見ると、干されるほどの悪い出来だとは思えない。ただし、全体に誠実な演出であるが、回想場面でオフボイスでの一人称視点を採用したり、ふいにキャメラを傾けたりと、デビュー作にありがちな野心ばかりが空転している箇所も散見され、積極的に擁護できるような出来ではない。
しかし高岩が『蜘蛛の街』の監督に鈴木を推薦したのは、鈴木が以前にシナリオ・コンクールに応募したシナリオを高く評価し、大映の前身である新興キネマ大泉撮影所に入社するきっかけを与えたのが高岩であったからだった。そればかりでない。高岩は、その後も鈴木が助監督のかたわら、シナリオをせっせと書き、そのうちのひとつ、舟橋聖一の短篇小説を脚色した『母代』(1941年、田中重雄監督)が入社1年目で映画化されたこともある鈴木を脚本の書ける監督として認め、鈴木の秘めたる能力を高く評価していたのだ。
プロデューサー三浦信夫は、第三次東宝争議が時間外手当の扱いをめぐって勃発したことを踏まえて、この作品をいかに低予算でもおもしろい映画を作れることの証明として、ロケーションを多用し隠し撮りも採用したセミ・ドキュのスタイルで撮影し、ギャランティのあまり高くないスターバリューのない俳優を起用し、事前に綿密なコンテと香盤表を作るという、合理的な撮影方式で製作費を切りつめて映画を成立させることにした(最終的にかかった直接製作費は破格の780万円だった)(「読売新聞」1950年6月10日付朝刊)。長い冷飯生活から突然監督に指名された鈴木英夫にとっても監督第2作、もう失敗は許されず、この一作にすべてがかかっていた。