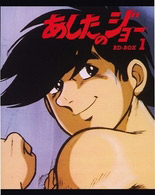映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦
第55回 60年代日本映画からジャズを聴く その13 「ジャズじゃない」時代の八木のジャズ映画音楽
第55回 60年代日本映画からジャズを聴く その13 「ジャズじゃない」時代の八木のジャズ映画音楽
八木正生の音楽的スタンスの捉えにくさ
八木正生の捉えにくさはどこにあるのだろうか。「捉えにくさ」と書いてしまうとかえって奇異の念を持たれるかも知れない。ジャズ・ピアニストとしても映画音楽家としてもある時期の日本を代表する人として彼は遇されてきたのだし、サザンオールスターズとの仕事「ステレオ太陽族」(ビクター音楽産業)のアレンジのように若い世代からのリスペクトが明らかなものもある。当時はそう受け取られていなかったがテレビアニメ『あしたのジョー』の音楽も、今振り返ればそうした敬意の表明の一端であったことは既に記してきたとおり。特に彼の音楽が「捉えにくい」と思われてきたことはなかったし、「捉えられた」からこそ、現にこうして一年以上様々な音源を紹介しながら聴いてくることも可能だったわけだ。とりわけサントラのコンピレーション・アルバム「八木正生の世界」(東宝ミュージック、ポリスター)は優れた成果で、ここでセレクトされた音源と彼自身の貴重なインタビューのおかげで映画音楽家・八木正生の姿は十分明らかにされている。だからそうした貴重な試みの成果を享受した上で言わせてもらうことになるわけだが、八木の音楽には、その根っこがたまたまジャズであったに過ぎないような感触があり、言い換えれば「映画音楽家にしてジャズ・プレイヤー」といった二面性――というか両面性――をほとんど感じさせないのだ。
さて、そう書いて前回のラストの言葉を思い出すと逆にすんなりと納得されてしまうところがあり、さらに言葉を費やさざるを得ない。改めて示しておくと、彼は座談会ではっきり「ジャズにはファンとして接していて自身はジャズ演奏家ではない」というくくり方をしていたのだったが、しかし「自分でそう言っているのだからそうなんだろう、ジャズ・プレイヤーじゃなくて八木正生はジャズ失格の映画音楽家なんだろう」、そう思われてしまうと、私がこだわっている問題からさらに離れてしまいそうなのだ。つまり私が八木正生の音楽を聴いて思うのは、いつでも、今その時彼のいるところとは別なところから音楽を演出しているかのような彼のスタンスなのである。単純化して言ってしまうと、彼はあたかも映画音楽家の余技のようにジャズを演奏し、ジャズ演奏家の趣味のように映画音楽をやり、アレンジャーの余技のようにソロピアノを弾き、ピアニストの余技のようにセロニアス・モンクを研究する。こういうスタンスを批判的に解釈すると、例えば相倉久人のように映画音楽家たる八木を低く見積もることになるわけだ。八木の音楽の「捉えにくさ」とはそういう意味においてである。
近年復刻なったジャズ・ピアニスト八木の代表作「セロニアス・モンクを弾く」(原盤キング、Think!)の解説を読むと鈴木秀人がこんなことを書いている。
八木のピアノはタッチなどを含めモンクを良く研究しており、驚くべき成果を示しているが、本作の前後に吹き込まれた作品を聴いてみると、モンクを感じさせない演奏が多いのも事実で、八木自身にとってはモンクを研究するということ自体、自身の音楽のほんの一部だったのではないかと思えるのだがいかがだろうか。
ここには、八木のそういう音楽的スタンスへのあからさまな批判という視点はないが、それは多分十分な歳月を経て、本作が既に名作の評価を確立しているためである。このモンク寄りの演奏を単なる物まねジャズとして非難する者がいてもそれ自体おかしくはないように思う。いや、ここではっきりさせてしまおう。前回の最後に引いた彼の言葉に寄りそうならば、当の八木正生自身がこのアルバムに対してそう思っていたとしても全然おかしくないのではないだろうか。モンクに衝撃を受け、その音楽を吸収し、そこからモンクを「弾く」アルバムを作っても、モンクの外へは一歩も出られなかった、そう八木が考えていた可能性は十分ある。
ただしそれを八木の音楽的挫折と捉える必要もない。つまりそこが先に述べたように八木の八木たるゆえんであって、モンクを弾くならばここまでやるという態度を徹底することで逆にその限界を示しているのである。録音当時そう感じていたかどうかは分からないが、少なくとも、ことさらに「日本人がジャズをやる」ことの限界性を述べていた時点での彼がそう感じていたのは確かである。本作が「プレイズ・モンク」物の世界的にも先駆け的な位置にあることを十分評価した上で、そういう冷めた視線こそ今必要ではないのか。「和ジャズ」だから何でも良し、という昨今の風潮は、演奏していた人たちが生きていたらかえって不愉快に感じたに違いない。「“和ジャズ”じゃなくて、ただの“ジャズ”としての評価はどうなんだ」と。