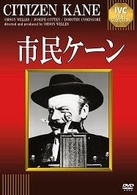海外版DVDを見てみた 第34回 オーソン・ウェルズの未公開作、未完成作 Text by 吉田広明
今年(2015年)はオーソン・ウェルズの生誕百周年に当たり、10月から11月には東京国際映画祭協賛でフィルム・センターにおいてウェルズを巡るドキュメンタリー上映、未完作品の断片の上映つきの講演会なども開かれた。今年になってイギリスではMr. Bongoから、『市民ケーン』以前の映画『ジョンソンにはうんざり』と、完成した作品としては最後から3番目のTV作品『不滅の物語』、そして『フォルスタッフ』のレストア版の、それぞれBlu-ray、DVDが発売された。『フォルスタッフ』についてはIVCから日本版Blu-rayが出ることになっており、それには筆者がリーフレット解説を書いている。興味のある方はご一読。ここでは残りの2作品について書く。
揺れる鐘の映像から始まり、その鐘を吊るしている滑車の上に老婦人が座っている(頬に真っ黒い線を入れたような老けメイク)。この女性を演じているのは当時のウェルズの妻(ウェルズは19歳で、在学中で既に結婚していた)。そこに階段上から男(ウェルズ自身が演じる、これも骸骨を思わせる老けメイク)がやってきて話しかけるのか、あるいは揶揄っているのか。鐘を鳴らそうとしきりに綱を引っ張っていた黒人(靴墨を塗っている)が絞首されて死ぬ(イラストで表される)。場面変わって、ウェルズ扮する男がピアノを弾く。音の出ない鍵盤がある。ピアノのふたを開けてみると先ほどの夫人が首にロープらしきものを巻きつけて死んでいる。男は「安らかに眠れ」、「神の身元に」など書いた紙をめくり「終」と書いた紙を選び、それが大写しになって映画は終わる。
鐘を鳴らすのを邪魔する女性は、あるいは自身の弔鐘を妨げているのかと思われる。ウェルズの母はピアニストで、彼が九つの時に死んでおり、ここに登場する女性はウェルズの母なのかと思わないこともない。いずれにせよ習作ではあって、ここに後年のウェルズを見ることは難しいように思われる。
人妻と浮気しているところを見つかった男(コットン)は非常階段から逃げる。夫は彼を追い掛けるが、その際妻が持っていた男の写真を持ちだそうとする。妻が妨げようとして写真は半分に切れる。男と夫はニューヨークの町中を追いつ追われつ、夫は上半分しか映っていない写真の男を探して、町中の男の帽子を脱がして歩く。男は市場、下町の倉庫やアパートメントの屋上と逃げ回るが夫はしつこく追ってくる。男はキューバ行きの船に。夫もそれに乗る。船にはメール・オーダー・ブライドとしてキューバに行く若い女性が乗っており、彼女を迎えるはずの夫の写真がこれまた男とそっくり。どういうなりゆきか判然としないが、男と夫は崖の上でフェンシングで対決し、最後に二人とも池のようなところに沈んで終わる。
映画は全体で40分、最初の20分が劇全体の導入として働き、二幕目、三幕目の導入としてそれぞれ10分。しかしディスクには67分の映像が収められている。同じようなショットが立て続けで出てきたりするので、テイク違いも全部つなげてあるものと思われる。冒頭部では追い追われる二人が船に乗るまでを映画で上映、以降演劇となって、舞台の上には船のデッキのセットがしつらえられている、という具合に映画と演劇がつなげられる予定だった。また第二幕のための導入としては船のデッキからキューバのジャングルが船からの移動撮影で捉えられ、カット代わって、背後に張り子細工で作った火山を控えたプランテーションの屋敷の模型にカメラが近づいてゆき、映画が終わると舞台はその屋敷セットになっている。この場面は『市民ケーン』におけるケーンの屋敷ザナドゥのパン撮影場面を思わせるという(フランク・ブラディによるアメリカン・フィルム・マガジン1978年11月号の、本作に関する最も詳細な記事「オーソン・ウェルズの失われた映画」より)が、このショットは残念ながら本盤には収められていない。上掲した記事は本作が失われていると思われていた時点での関係者の証言を元に書かれているので記憶違いなのか、撮られたが無くなったのか判然としないが、全体を見てもあまり後年のウェルズを思わせるところの少ない作品なので、そのような場面があったとすれば是非見てみたかったものである。
この作品で最も長い時間を占めるのがコットンと寝取られ夫を演じる鬚の男エドガー・バリアーの追っかけ。バッテリー・パークやセントラル・パーク、そしてフルトン魚市場、ダウンタウンなど、ニューヨークの、19世紀の面影を残した場所をロケ地としている。市場では魚用なのだろうか、桶のようなものがランダムに積み重ねられている間を二人が見え隠れに追いかけっこを延々演じる。また古いビルの屋上に上がって隠れるコットンを、切妻の明り取り窓からバリアーが首を出して探すという場面も場所を変えながら何度も繰り返されるが、こうした場面では、切妻の明り取り窓、複雑に入り組んだダクト、臭い逃がしの煙突など、当時残っていた建築物のドキュメントとして見ることができる(写真家ポール・ストランドと画家チャールス・シーラーによる、都市ドキュメンタリー実験映画『マンハッタ』(21) に比する人もいる。これもYoutubeに上がっている)。周囲のビルの窓から眺めている野次馬の姿なども見え、ゲリラ撮影だったことが分かる(まあ、そうだろうけど)。
上演劇場に映写設備がないことが明らかになり、撮るだけは撮ったが編集もされないままフィルムは放置され、劇自体は映画部分無しで試演されたものの不評で結局レパートリーから取り下げられ、上記のようにウェルズの別荘にしまい込まれることになったわけだが、本作でウェルズは初めて本格的に映画の撮影、編集に取り組むことになり、その意味で重要な作品である。特に上演と上映を組み合わせるというアイディアは、その後のウェルズが、例えばラジオ『宇宙戦争』(この作品の直後である)や『市民ケーン』で、ニュースの体で虚構を描き、現実と虚構の境目を曖昧にしたり、『フェイク』で、偽物を巡る実話とホラ話との境界を曖昧にしたりしたことの萌芽のようにも思える。
マカオ(原作ではカントン)の老商人クレイ(オーソン・ウェルズ)は、商売仲間を破滅させ、その広大な屋敷を抵当に取り、一人暮らしている。鏡ばかり多いその屋敷で、日がな一日秘書ルビンスキに古い書類を朗読させているクレイは、かつて船上で聞いた物語を思い出す。老商人が若い妻を妊娠させるのに5ギニーで船員を雇うという物語。その物語は船員の間に伝わり、何度も何度も繰り返し語られている物語だった。作り話が大嫌いなクレイは、その物語を現実のものにしようとする。選ばれた若い女ヴィルジニー(ジャンヌ・モロー)はかつての商売仲間の娘だった。クレイは路上で一人の船員ポールを拾い、二人にベッドを共にさせる。クレイへの復讐心から、クレイが父を破滅させたのと同じ金額20ギニーを吹っ掛けたヴィルジニーだったが、その復讐心は翌朝きれいに消え去っていた。一方船員はクレイに貝殻を与えて去る。クレイはそれを耳に当て、いつか聞いたことのある波音に耳を傾けるが、そのまま死ぬ。
何といっても、ホラ話ばかり映画でしてきたウェルズが、ホラ話の嫌いな男を演じるという逆説に注意が向く。しかしそのホラ話が現実のものになってしまったために彼は死ぬわけで、するとホラ話がホラ話である間だけ、彼は生きていられるということでもある。ならば見た目は逆であっても、実のところホラ話を糧に生きてきたウェルズその人の物語だったとも見える。マカオで船員が巻き込まれる物語、という意味では『上海から来た女』(45)を連想させもする。しかし鏡の多い屋敷とされながらも、鏡によってイメージが多重化されるような外連、『上海から来た女』の有名なラストや、あるいは『審判』(62)における、鏡と透明なガラスを交互に配し、その前を走り抜ける女のイメージが映っては消える弁護士(ウェルズ自身が演じる)事務所壁面の、単純ながら不可思議なイメージなどからは程遠い。実際この作品はウェルズにとって初めてのカラー作品ということもあるが、これまでのウェルズ作品とはかなり趣が異なる。カメラを傾けるようなこともほぼなく、クロノロジーも直線的で、時空間の歪みはない。また比較的クロース・アップが多いのもウェルズらしからぬ点だ。とりわけそれはヴィルジニーと船員のラブ・シーンに見られる。そもそもラブ・シーン自体がウェルズにとって稀なものなのだ。ウェルズには存外エロティシズムは少ない(直ぐに多い浮かぶ例としては『オセロ』で、デズデモーナを覆う白い死のシーツに彼女の鼻や唇の形が浮き上がる場面くらいだろうか)。この場合にしてもモローの裸が映るわけでもない(裸の後ろ姿が映らないこともないが、代役の可能性もある)。演出そのものを目立たせるというより、原作の物語の忠実な映画化を目指したのではないかという気がする。たまたまモローが出演しうる作品と言うことでこの短編ばかりが残ってしまい、作品数が多いわけではないウェルズの完成作ということで見るとどうも味が薄いように思えるのだが、ウェルズ自身が凄い物語だとしている『ア・カントリー・テール』などが撮られていれば、あるいはそちらの方が凄いものになっていたのではないかという気がする。
『年の心』
ウェルズにはこれ以前に短編があるので先ずそれについて。『年の心』Hearts of ageと題されたそれは1934年、まだウェルズが寄宿制の男子校トッド・スクールに在籍していた頃の16ミリ・フィルム、総計8分でサイレント。
Youtubeなどにも上がっているので見ることが可能。
揺れる鐘の映像から始まり、その鐘を吊るしている滑車の上に老婦人が座っている(頬に真っ黒い線を入れたような老けメイク)。この女性を演じているのは当時のウェルズの妻(ウェルズは19歳で、在学中で既に結婚していた)。そこに階段上から男(ウェルズ自身が演じる、これも骸骨を思わせる老けメイク)がやってきて話しかけるのか、あるいは揶揄っているのか。鐘を鳴らそうとしきりに綱を引っ張っていた黒人(靴墨を塗っている)が絞首されて死ぬ(イラストで表される)。場面変わって、ウェルズ扮する男がピアノを弾く。音の出ない鍵盤がある。ピアノのふたを開けてみると先ほどの夫人が首にロープらしきものを巻きつけて死んでいる。男は「安らかに眠れ」、「神の身元に」など書いた紙をめくり「終」と書いた紙を選び、それが大写しになって映画は終わる。
鐘を鳴らすのを邪魔する女性は、あるいは自身の弔鐘を妨げているのかと思われる。ウェルズの母はピアニストで、彼が九つの時に死んでおり、ここに登場する女性はウェルズの母なのかと思わないこともない。いずれにせよ習作ではあって、ここに後年のウェルズを見ることは難しいように思われる。
『ジョンソンにはうんざり』
『ジョンソンにはうんざり』Too much Johnsonは厳密に言えば映画作品ではない。もともとは演劇の冒頭や幕の導入部として上映されるべく撮影された素材であり、しかも結局使われずじまいで編集されないまま放置されていたものを、劇の順序通りつなげたものに過ぎない。失われたものと思われていたが、ウェルズのマドリードの別荘にあるのが見つかり、ウェルズは編集してコットンへの贈り物としようと考えた。しかしこの別荘が火事になり、結局再びその際に失われたと考えられていた。しかし2013年イタリアにあるのが発見されて見られるようになり、ボルデノーデ無声映画祭で上映された。1938年、マーキュリー劇団の2年目の始め、演劇の秋シーズン開始作品として、ゲオルク・ビュヒナー『ダントンの死』と共にレパートリー候補として挙げられた。原作はウィリアム・ジレット作のコメディ。コメディ『馬が食べた帽子』(ルネ・クレールが『イタリア麦の帽子』(27)として映画化したこともある)を1年目の演目として演出したウェルズが、ジョゼフ・コットンに喜劇の才能があることを発見し、これを上演演目に入れた。人妻と浮気しているところを見つかった男(コットン)は非常階段から逃げる。夫は彼を追い掛けるが、その際妻が持っていた男の写真を持ちだそうとする。妻が妨げようとして写真は半分に切れる。男と夫はニューヨークの町中を追いつ追われつ、夫は上半分しか映っていない写真の男を探して、町中の男の帽子を脱がして歩く。男は市場、下町の倉庫やアパートメントの屋上と逃げ回るが夫はしつこく追ってくる。男はキューバ行きの船に。夫もそれに乗る。船にはメール・オーダー・ブライドとしてキューバに行く若い女性が乗っており、彼女を迎えるはずの夫の写真がこれまた男とそっくり。どういうなりゆきか判然としないが、男と夫は崖の上でフェンシングで対決し、最後に二人とも池のようなところに沈んで終わる。
映画は全体で40分、最初の20分が劇全体の導入として働き、二幕目、三幕目の導入としてそれぞれ10分。しかしディスクには67分の映像が収められている。同じようなショットが立て続けで出てきたりするので、テイク違いも全部つなげてあるものと思われる。冒頭部では追い追われる二人が船に乗るまでを映画で上映、以降演劇となって、舞台の上には船のデッキのセットがしつらえられている、という具合に映画と演劇がつなげられる予定だった。また第二幕のための導入としては船のデッキからキューバのジャングルが船からの移動撮影で捉えられ、カット代わって、背後に張り子細工で作った火山を控えたプランテーションの屋敷の模型にカメラが近づいてゆき、映画が終わると舞台はその屋敷セットになっている。この場面は『市民ケーン』におけるケーンの屋敷ザナドゥのパン撮影場面を思わせるという(フランク・ブラディによるアメリカン・フィルム・マガジン1978年11月号の、本作に関する最も詳細な記事「オーソン・ウェルズの失われた映画」より)が、このショットは残念ながら本盤には収められていない。上掲した記事は本作が失われていると思われていた時点での関係者の証言を元に書かれているので記憶違いなのか、撮られたが無くなったのか判然としないが、全体を見てもあまり後年のウェルズを思わせるところの少ない作品なので、そのような場面があったとすれば是非見てみたかったものである。
この作品で最も長い時間を占めるのがコットンと寝取られ夫を演じる鬚の男エドガー・バリアーの追っかけ。バッテリー・パークやセントラル・パーク、そしてフルトン魚市場、ダウンタウンなど、ニューヨークの、19世紀の面影を残した場所をロケ地としている。市場では魚用なのだろうか、桶のようなものがランダムに積み重ねられている間を二人が見え隠れに追いかけっこを延々演じる。また古いビルの屋上に上がって隠れるコットンを、切妻の明り取り窓からバリアーが首を出して探すという場面も場所を変えながら何度も繰り返されるが、こうした場面では、切妻の明り取り窓、複雑に入り組んだダクト、臭い逃がしの煙突など、当時残っていた建築物のドキュメントとして見ることができる(写真家ポール・ストランドと画家チャールス・シーラーによる、都市ドキュメンタリー実験映画『マンハッタ』(21) に比する人もいる。これもYoutubeに上がっている)。周囲のビルの窓から眺めている野次馬の姿なども見え、ゲリラ撮影だったことが分かる(まあ、そうだろうけど)。
上演劇場に映写設備がないことが明らかになり、撮るだけは撮ったが編集もされないままフィルムは放置され、劇自体は映画部分無しで試演されたものの不評で結局レパートリーから取り下げられ、上記のようにウェルズの別荘にしまい込まれることになったわけだが、本作でウェルズは初めて本格的に映画の撮影、編集に取り組むことになり、その意味で重要な作品である。特に上演と上映を組み合わせるというアイディアは、その後のウェルズが、例えばラジオ『宇宙戦争』(この作品の直後である)や『市民ケーン』で、ニュースの体で虚構を描き、現実と虚構の境目を曖昧にしたり、『フェイク』で、偽物を巡る実話とホラ話との境界を曖昧にしたりしたことの萌芽のようにも思える。
『不滅の物語』
『不滅の物語』はデンマークのアイザック・ディーネセンの同名の短編の映画化。元々はブタペストでディーネセンの短編を5篇ほど集めて1本の映画にする予定(そのうちもう1篇の作品は取り替えられた子供たちの物語『ア・カントリー・テール』とウェルズは述べているが、ディーネセンのどの作品に当たるかは不詳)で企画が進められていたが、出資者が逃げ出し、ウェルズはホテルの払いもそこそこにブタペストを去らねばならなかった。その後ジャンヌ・モローが出るということで『不滅の物語』にフランスのTV、ORTFが出資、その1篇のみ完成したもの。マカオ(原作ではカントン)の老商人クレイ(オーソン・ウェルズ)は、商売仲間を破滅させ、その広大な屋敷を抵当に取り、一人暮らしている。鏡ばかり多いその屋敷で、日がな一日秘書ルビンスキに古い書類を朗読させているクレイは、かつて船上で聞いた物語を思い出す。老商人が若い妻を妊娠させるのに5ギニーで船員を雇うという物語。その物語は船員の間に伝わり、何度も何度も繰り返し語られている物語だった。作り話が大嫌いなクレイは、その物語を現実のものにしようとする。選ばれた若い女ヴィルジニー(ジャンヌ・モロー)はかつての商売仲間の娘だった。クレイは路上で一人の船員ポールを拾い、二人にベッドを共にさせる。クレイへの復讐心から、クレイが父を破滅させたのと同じ金額20ギニーを吹っ掛けたヴィルジニーだったが、その復讐心は翌朝きれいに消え去っていた。一方船員はクレイに貝殻を与えて去る。クレイはそれを耳に当て、いつか聞いたことのある波音に耳を傾けるが、そのまま死ぬ。
何といっても、ホラ話ばかり映画でしてきたウェルズが、ホラ話の嫌いな男を演じるという逆説に注意が向く。しかしそのホラ話が現実のものになってしまったために彼は死ぬわけで、するとホラ話がホラ話である間だけ、彼は生きていられるということでもある。ならば見た目は逆であっても、実のところホラ話を糧に生きてきたウェルズその人の物語だったとも見える。マカオで船員が巻き込まれる物語、という意味では『上海から来た女』(45)を連想させもする。しかし鏡の多い屋敷とされながらも、鏡によってイメージが多重化されるような外連、『上海から来た女』の有名なラストや、あるいは『審判』(62)における、鏡と透明なガラスを交互に配し、その前を走り抜ける女のイメージが映っては消える弁護士(ウェルズ自身が演じる)事務所壁面の、単純ながら不可思議なイメージなどからは程遠い。実際この作品はウェルズにとって初めてのカラー作品ということもあるが、これまでのウェルズ作品とはかなり趣が異なる。カメラを傾けるようなこともほぼなく、クロノロジーも直線的で、時空間の歪みはない。また比較的クロース・アップが多いのもウェルズらしからぬ点だ。とりわけそれはヴィルジニーと船員のラブ・シーンに見られる。そもそもラブ・シーン自体がウェルズにとって稀なものなのだ。ウェルズには存外エロティシズムは少ない(直ぐに多い浮かぶ例としては『オセロ』で、デズデモーナを覆う白い死のシーツに彼女の鼻や唇の形が浮き上がる場面くらいだろうか)。この場合にしてもモローの裸が映るわけでもない(裸の後ろ姿が映らないこともないが、代役の可能性もある)。演出そのものを目立たせるというより、原作の物語の忠実な映画化を目指したのではないかという気がする。たまたまモローが出演しうる作品と言うことでこの短編ばかりが残ってしまい、作品数が多いわけではないウェルズの完成作ということで見るとどうも味が薄いように思えるのだが、ウェルズ自身が凄い物語だとしている『ア・カントリー・テール』などが撮られていれば、あるいはそちらの方が凄いものになっていたのではないかという気がする。