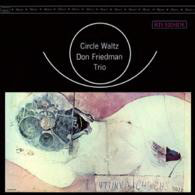映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦
第68回 人間国宝ジャズ 山本邦山追悼その6
第68回 人間国宝ジャズ 山本邦山追悼その6
邦山とピアニスト佐藤允彦
山本邦山とジャズとの関わりは音楽的に二つに分けられる、と前回記してある。「リズムの明瞭な拍節的音楽」と「間を活かす空間的音楽」である。正確には、彼はそれを「現代の尺八音楽」の二つの方向性として示したのだが、その違いが彼のジャズ尺八にもぴたりと当てはまるものであることを、具体的にアルバム・タイトルを挙げて提示しておいた。前者が例えば原信夫とシャープス・アンド・フラッツと組んだ諸作品であり、後者が山下洋輔、富樫雅彦と組んだドイツ制作のアルバムということになる。どちらが上等ということではなく、どちらもジャズとして楽しめればそれで良いのだが、ただし前者において邦山の即興演奏パートは多くの場合アレンジャーによって予め記譜されたものであったのに対して、後者では彼自身の音楽的フィールドである邦楽の方法論によって演奏されたものだった、という違いがある。従って即興という言葉の定義を正確に捉えれば、後者をこそ「邦山の即興演奏」と呼ぶべきだとは言える。山下、富樫、菊地雅章といったフリー系ジャズメンが後者のアルバムに参加し、一方、前田憲男、山屋清に代表されるモダン・ジャズ編曲家が前者を活気づけていること。さらに言えば佐藤允彦がいわば「両者をつなぐ」ような人材として機能したことも重要なポイントであった。今回はまず後者の系譜を(やはり若干のアルバム・タイトルを挙げながら)邦山が参加しているか否かにこだわらず示していくことにしよう。
本連載でいずれ佐藤允彦、菊地雅章、富樫雅彦は取り上げる。つまり彼らの映画音楽に注目するつもりだから、それらの楽曲とアルバムは今回スルーしておく。ともあれ佐藤允彦のプロフィールをアルバム「パラジウム/佐藤允彦トリオ」“Palladium”(東芝EMI)から紹介しよう。執筆は岩浪洋三。
佐藤允彦は1941年10月6日東京都に生まれ、慶應義塾大学経済学部を1964年に卒業している。高校時代からジャズの世界に入り、ジョージ川口とビッグ・フォー・プラス・ワンに加わって演奏、大学時代には高見健三とミッドナイト・サンズ、稲垣次郎クインテットなどで演奏し、若くしてピアニストとしての才能を発揮した。64年からは自己のトリオで演奏して注目されたが、66年にダウンビート誌の奨学金を得てボストンのバークリー音楽院に留学した。68年9月には1年早く留学していた荒川康男と一緒に帰国し、富樫雅彦を加えてトリオを作った。そのトリオによる第一作が『パラジウム』である。そしてESSG、がらん堂などを経て、CPU、シャドウマスク、ITSなどと演奏し、一時はかなりフリー・ジャズにも傾いたが、その後はソロ・ピアノで独自の世界を開拓した。
本アルバム、録音は69年だがこのライナーは20世紀最後の年の再発CD用に書かれたものだ。従って本盤の歴史的意味とかは既に総括され尽くしていて、淡々とした書きぶり。ところが私は、もちろん購入した際にはライナーを読んでいるものの今回久しぶりに棚から引っ張り出してきてこれを読み、結構分からない部分があるのに困惑している。実はバークリー留学以前の佐藤を多分一枚も聴いたことがないせいだ。だから最初期佐藤のキャリアについては今後の宿題にしておこう。
そこで本「パラジウム」の単独で持つ意味である。近年の「和ジャズ」ブームでスポットを浴びた商品がどちらかというと「埋もれた作品」や「忘れられた作品」に焦点を改めて当てる意図によるものだったのに対して、「パラジウム」は最初にリリースされた時点から大きい注目を集めたという特色があり、今はなき雑誌「スイングジャーナル」主催のジャズ・ディスク大賞第三回日本ジャズ賞を受賞している。ではこのアルバムの何が人々の心を捉えたのか。構成から見ると短い「オープニング」と同じく短い「クロージング」を挟んで全六曲から成る緩やかな組曲とも言える。
佐藤によるメモ風のごく簡略な解説を以下全文引こう。①オープニング:プリペアード・ピアノ、インドの鈴、アルコ。②ミシェル:奇妙な混合―インド、ヨーロッパ、アメリカ―そのどれでもない。③ザルツブルグの小枝:「―塩抗に放りこまれた枯枝に、塩の結晶が附着して、やがてダイアモンドのように輝く―」(この言葉はスタンダールが「恋愛論」の中で恋について語った一節である。岩浪注)④パラジウム:合金の一種。⑤スクローリン:渦。うず。⑥クロージング:―幕―。また「ミシェル」は言うまでもなく有名なビートルズのナンバーで、留学中にボストンのバンド「ジーン・ディスティションとブラス‘68」の依頼を受けて編曲したものが元になっている。「パラジウム」と「ザルツブルグの小枝」は奨学金資金獲得のため事務局に応募(提出)した曲。「スクローリン」は新曲。吹き込み当日に書きあげたもの。以上の情報もライナーに基づく。
組曲と言ってもブックエンド的な並びでそう感じさせるだけと分かる。このアルバムをリアルタイムで体感しているわけではない私が、初めて本作を聴いたのは80年代の初頭のことだと思うが聴く前から「聴きどころ」と認識していたのは「ミシェル」だった。もちろん大満足。ジャズ初心者(私のこと)にも良く分かった(つもりになった)。他の曲のタイトルからも類推できるようにアルバムに流れる雰囲気は硬質な抒情であり、知的な耽美性である。先行するのはビル・エヴァンスだとしても、そのエヴァンス性をさらに純化させる試み、と言うべきか。それをとりわけ現出させるのが「ミシェル」で、ここで少し説明をする。
こうした一団のピアニストをジャズ史的には「エヴァンス派」とくくることになっていて、とても便利な言葉なのだがくくられた側は多分迷惑だろう。その一例。この一派の走りというべきドン・フリードマンの代表作「サークル・ワルツ/ドン・フリードマン・トリオ」“Circle Waltz”(RIVERSIDE)を手に取りクレジットを読むと録音は62年で、エヴァンスと同時代的な音楽だと分かる。エヴァンスと組む以前のスコット・ラファロをフリードマンがレギュラー・ベーシストにしていたり、またラファロ亡き後エヴァンス・トリオのベーシストに抜擢されたチャック・イスラエルがやはりフリードマン・トリオのメンバーで現にこのアルバムに参加していたり、とこの二人のピアニストは奇しき因縁を感じさせる部分もある。
だからといって「似ているのは偶然だ」とか「全然似てない。似てると言ってるヤツは耳が悪いだけ」とか主張するのはやっぱり無茶で、同じ時代に生きているんだから影響されたんですよ、それでいいんじゃないかと思う。事実このアルバム以前のフリードマンのジャズが「バド・パウエル・スタイルの典型だった」という証言もある。もっともフリードマン自身、エヴァンスから影響された事実はない、と、かつて語っていたそうだが今ではそうでもないのではないかな。フリードマンがエヴァンスほど有名になれなかったのは「エヴァンス的すぎた」からであり、それはそれで仕方なかろう。批評家板橋純は両者の「違い」を「フリードマンがエヴァンスを研究しきったところからくる、エヴァンスよりエヴァンスらしいピアノを弾くピアニストだといえることではないだろうか」とまで書いているほどだ。影武者は優れていればいるほど本家の方を輝かせるしかないわけで、それが影武者の存在意義なのだろう。
だから確かに「一番迷惑をこうむったのはフリードマン」ではあり、ここまでは「エヴァンス派」のいわば前提というか宿命。しかしフリードマンがエヴァンスを超えた部分があるとすれば、それが先に述べたように、エヴァンスをさらに純化させたかのような音楽的印象なのだ。音楽的印象を音楽的に説明するのは、私じゃ能力的に無理なのでここは適当に対処するしか手はないがアルバム「サークル・ワルツ」をまずは聴いていただいて、とりわけそのタイトル曲の美しさに浸っていただきたい。エヴァンスから影響された覚えはない、とフリードマンが大見得(おおみえ)を切った時、彼が言いたかったのは、少なくともこのアルバムは「美しさにおいて」エヴァンスよりも先を行っているという自負だったに違いないのだ。それが「より純化された」エヴァンス・ミュージックということで、「パラジウム」っぽく言えば「音」の結晶化、クリスタライゼーションということになる。つまり動物的な生気というより鉱物的な永遠性の印象である。こうしたピアニストの代表として他にスティーヴ・キューンがいる。68年録音のアルバム「ウォッチ・ホワット・ハプンズ!」“Watch What Happens!”(MPS)や74年の「トランス」“Trance”(ECM)を聴いていただきたい。特に後者を。またリッチー・バイラークの「エレジー〜ビル・エヴァンスに捧ぐ」“Elegy for Bill Evans”(VENUS)も必聴盤。エヴァンスが亡くなったのは80年9月15日で本盤リリースは81年、従って録音もその頃だと分かる。バイラークはプロになるより前に、伝説的なビル・エヴァンス・トリオの伝説的な最後のライヴを客席で聴いているくらいだから、フリードマン的な屈折は最初からない。本盤はエヴァンスのコピーではないバイラークのジャズを、しかもエヴァンスでおなじみの楽曲を素材にして作り出すというコンセプトで、追悼盤といっても悲しみに浸りきった音楽とは違う。一種の「卒業論文」のような音楽。
そして、聴取の印象で大ざっぱに述べさせてもらうといわゆる「エヴァンス派」というのは、本家エヴァンスよりも分家フリードマンのジャズの官能的な質感を継承するものだと言える。つまりエヴァンス派とはむしろ「ポスト・エヴァンス」の傾向を有する。「パラジウム」に聴かれる「ミシェル」もそうした演奏の典型で、ベース音のひたすらな繰り返しと、対照的に散発的なパーカッションがゆっくりと進むうちにやがておなじみの旋律がピアノで入ってくる瞬間のぞくぞくする感じは筆舌に尽くしがたい。キューンで言えば68年の音から74年の音へと、ちょっと聴くだけで何かが変わったと誰でも分かる、その変化後の音が、この「ぞくぞくする感じ」なのだが、どう変わったか説明せよと言われても、再三申し上げているように私じゃ音楽的には説明できないのだ。ただエヴァンスのジャズよりも官能的で、もっと繊細な何か、としか言えないのである。
佐藤がバークリーで学んだことの一つは楽理的な「エヴァンス的ハーモニー」のつけ方だった、と彼自身インタビューで語っているから、アルバム「パラジウム」がそうした成果の発表の場であったのは、とりあえず間違いではないはずだ。ただし「パラジウム」は「サークル・ワルツ」からでも既に七年が経過している。エヴァンスに似ているとされてフリードマンが苛立つ、といった時代は既に終わっており、エヴァンス派はそれを発展させた「ポスト・エヴァンス派」を潜在的に包含する、一つの正統的なピアニストのスタンスとして確立していた。もっとも、ここで確認しておきたいのはエヴァンスの後継者達の方がエヴァンスよりも官能的だからといって、それがエヴァンスに対する優越性の証明ではない、という点である。ビル・エヴァンスは(ポスト)エヴァンス派よりも複雑で巨大な音楽家であり、官能性というピンポイントで後継者に劣る分、さらに混沌としている。佐藤にとってエヴァンスはいわば咀嚼されるべき対象であり、そこから彼が自分の音楽を作り上げていくための主要な方法論なのだ。出発地点、もしくは再出発地点としてのエヴァンスとでも言えばいいか。佐藤はやはりインタビューで、留学以前のある日、ジャズクラブの仕事でオスカー・ピーターソン・スタイルのピアノを演奏していたところ、気づいたら後ろに来日中の本人が立っていて冷や汗ものだった、という経験を語っている。真似がいくら上手くても本人にはなれない。そう気づかされた、と。
バークリーで佐藤が得たのは、だから「エヴァンス風にピアノを引く技術」ではない。技術というなら、エヴァンスから何を引きだすかという技術であり、エヴァンスに自分はさらに何を付与できるか、という覚悟、自問でもある。つまり「パラジウム」はまさにこの技術と覚悟の相乗効果なのだ。通常佐藤をわざわざエヴァンス派とくくることはないが、「ミシェル」の根幹にあるのはポスト・エヴァンス的な抒情である。そしてそこに何を付与し得たと問うならば、それはフリー・ジャズ的な、つまり「即興演奏の方法の自由度をさらに拡張させた音楽」の側面なのだ。佐藤のアルバムにインスピレーションを与え、後押ししたのがトリオのドラマー富樫雅彦であった。