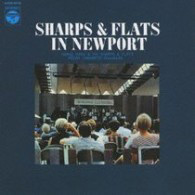映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦
第64回 人間国宝ジャズ 山本邦山追悼 その2
第64回 人間国宝ジャズ 山本邦山追悼 その2
ニューポートの「シャープス&フラッツ」と山本邦山
「1967年7月2日、原信夫とシャープス&フラッツは、ある有名なジャズ祭のステージに立っていた。アメリカ東海岸にある最も古いリゾート地、ロードアイランド州ニューポートで開かれてきた、世界最大といわれるジャズフェスティヴァルである。」(「シャープス&フラッツ物語」長門竜也 著、瀬川昌久 監修、小学館刊)。既に66年末、正式に出演の打診はあったし、主催者ジョージ・ウェインの意向は数年前から日本側に伝わってもいた。原としても参加したいのはやまやまだったのだが、問題はこの「ニューポート・ジャズ・フェスティヴァル」に出演しても出演者の懐には一銭も入らないことにあった。単純に言えばギャラなし、つまりこれは今で言う「ヴォランティア仕事」だったのだ。個人で出るならばそれもありだろうが二十人近いビッグ・バンド、しかも日本からその音楽祭の「ためにのみ」渡航するのである。現在と違い1ドルは360円。アメリカと日本の差とは何より経済的格差のことだった、そんな時代。単純に現在のレート(1ドル百円として)で比較しても3.6倍の重圧。実際には五から十倍くらいの経済格差感だったはずで、これはキツい。
原は結局メンバーの渡航費を自腹でかぶることにした。「ただ半月間におよぶアメリカ渡航と、それに要する様々な準備やフォローのいちいちが時間を要し、バンドの経済的支えとなっているその伴奏仕事さえ、以後は放棄せざるを得なくなるに違いなかった。」それでも、交通網の新時代が原に味方した、とは言える。日本航空(JAL)の国内線の拡充に伴う定期的なレセプション・パーティー等のPR仕事を率先して行うことで原は日航との関係を深めていたからだ。多少の融通は利くだろう。実際団体割引券を使い、乗客も積極的に募って準備運動は実を結び始めた。覚悟は決まった。
いったん覚悟を決めてしまえば時間はたっぷりとある。原はこのまたとない機会にアメリカ人の見知っているジャズと異なる「日本のジャズ」を提示したいと考えた。民謡や俗謡、つまり日本の伝統音楽のジャズ版というコンセプトである。作曲編曲陣として、原が白羽の矢を立てたのは「意欲的でありながら伝統的ジャズの語法に通じ、信頼が置けて、正確で、仕上げの早いチーム」、山屋清と前田憲男だ。この二人の名前は既に「モダンジャズ三人の会」のメンバーとして取り上げてある。彼らについてはもう一人のメンバー三保敬太郎との動向も合わせて次回以降に記述したい。そしてもう一つ、原は「それまで自身が見すごしていた日本の伝統楽器を参加させることも思いついた。」
というわけで、ここにようやく「前回からの続き」山本邦山の出番となる。前掲書より引用。
ヘレン・メリルというハスキーな歌手がかつて、尺八と一緒に日本の子守唄をレコードに吹き込んだことがあった。(略)編曲を担当したのはこの楽器のことを研究し尽くしていた前田憲男で、そこに聴く迫力ある尺八には惹かれるものがあり、山本の名は暗記していた。それですぐに相談を持ちかけると、二つ返事で即決してくれた。
メリルとの共演盤のことは前回述べた。今回はこのニューポートでの仕事の副産物「ニューポートのシャープス・アンド・フラッツ」“Sharps & Flats in New Port”(日本コロムビア)をまず紹介する。原自身によるライナーノーツから引用。
このレコードに収録された曲目のすべては1967年のニューポート・ジャズ・フェスティヴァルで「シャープス・アンド・フラッツ」が演奏したものです。このレコードをお聴きになったジャズ・ファンの皆さんは「シャープス・アンド・フラッツ」がなぜアメリカの曲を演奏しなかったのかと不思議に思われることでしょう。(略)ジャズは、アフリカからアメリカに労働力として移り住んだ黒人達の中から生まれました。(略)こうして黒人の中に生まれ育ったジャズですが、今では、勿論黒人のみならずあらゆる人種、世界中の人々の音楽になっていると言えるでしょう。(略)日本にも、古く戦前からジャズは輸入されていましたが、戦後になってアメリカ軍の進駐を迎えてから本格的なジャズが演奏されるようになり、20年余りの間に長足の進歩をとげて今日に至っています。アメリカのジャズの進歩に追いつきつつある今日、いつまでもアメリカの模倣や追従でなく日本で生まれたジャズがあっても当然ではないでしょうか。
本アルバムは実はライヴ録音ではない。バンドがニューポートで演奏した楽曲をスタジオで改めてレコーディングしたものだ。「箱根馬子唄」「さくらさくら」「越天楽」「ソーラン節」「阿波踊り」等、日本人なら誰でも知っている曲に原のオリジナル「古都」、明治の俗謡のジャズ版で数年前からレパートリーになっていた「梅ヶ枝の手水鉢」、邦楽「みだれ」、ボビー・ティモンズ作曲の「ソー・タイアード」“So Tired”を加えた全九曲。邦山は「みだれ」「箱根馬子唄」そして「ソー・タイアード」の三曲にだけ参加した。
原自身も大方の現代の日本人同様、伝統的な純邦楽に詳しくなかったのだが、ジャズフェスにプレゼンするコンセプトが決まってから和音階を改めて勉強し直し、その過程で尺八ジャズの可能性に目覚めたのであった。既に前田が邦山とジャズを音楽的に橋渡ししていたし、キング・レコードに所属していたジャズ評論家の久保田二郎がヘレン・メリルと親しかったことも邦山とジャズ界がスムーズに連動するのに役だった。原はまた「尺八を加えたということが単なる異国趣味だけでなく新しい演奏形態として評価され、尺八という楽器の良さを外国の人々に知ってもらえたこと」を大きな喜びと表現している。同時に「私も含めて多くの日本人が、今まで日本古来の音楽や楽器については知らないことが余りに多すぎました」と反省してもいる。
この二点が、というよりむしろ後者こそが、率直な原の実感であったことは今だからこそ認識できる。そして前者。この感想はアメリカでの観客の反応を直に体感し、咀嚼した上でのものであるのも明白だ。
山本邦山は著書「尺八演奏論」においてこの劇的なイヴェントをこう回想する。
ジャズの本場の檜舞台に、日本のジャズバンドが日本の民族楽器をもって挑戦しようというのはまさに大胆そのものであり、原信夫氏以外の誰が成功を予期しえたであろうか。しかし、氏の核心は的中し、大成功のうちに終わった。(略)ジャズが本場のアメリカで、ただの模倣ではない日本の本物を、という想いが一体となった結果といえようか。
邦山はもともとジャズ奏者ではないから、端的に言えば「ジャズの理論によるコード進行に基づく即興演奏」は出来ない。「《箱根八里》などの中にアドリブを入れなければならない。しかし、私にはまだまだその力はなかった。結局、優れたピアノ演奏家であり作・編曲の大家でもある前田憲男氏が書いてくれたものを、一生懸命練習して暗記したのである」と邦山自身述べている。こうしたことは邦山に限らずジャズとクラシック奏者の共演にはよくある。若き日、アンドレ・プレヴィンがハリウッドで重宝がられたのはピアニストのために事前に記譜してアドリブに見せかける能力にあったことは連載第28回に述べた。近年でもイツァーク・パールマンがプレヴィンとジャズっぽく音楽的対話を楽々と成し遂げたのは、実は記譜されたアドリブだったと言われる。一方で邦山は「なかでも、《みだれ》の原曲を抜粋・アレンジしたコントラバスと尺八のデュエットは、非常な好評を博した」とも記している。「みだれ」は彼のパリでの思いがけないデビューとなった58年の世界民族音楽祭で演奏した曲だったことは前回述べた。こちらはジャズ化バージョンとはいえ奇しき因縁だ。本作ライナーの楽曲解説では、本多俊夫(伊丹十三監督作品の音楽担当者として有名なジャズ・サックス奏者本多俊之の父。ジャズ評論家)が「山本邦山氏をフィーチュアした純日本的フーガともいうべき、甚だ魅力に富んだ、幻想的な演奏である。竹内弘のベースとのデュエットだが、実に見事なインタープレイを展開して満場をうならせた」とも。
本多は原と親しく、ニューポートに随行してそのレポートをアルバムに寄せている。
演奏は“さくらさくら”のモダン・ジャズ版で開始された。ゴキゲンなサウンドである。(略)プログラムが進むにつれて、我々客席にいる“日本人”は、本当に嬉しくなってきた。(略)私のうしろに陣取っていた黒人達が、「ビューティフル!」「マーヴェラス!」を連発している。シャープス・アンド・フラッツの演奏は、聴衆に大きな感動を与えたもののようだ。それは尺八の山本邦山氏の登場で頂点に達した感がある。紋付、袴に身を正した、この東洋の楽人が奏でる“バンブーフルート”の音色は、アメリカ人達の魂に触れる“何か”を持っていた…。
原信夫とシャープス・アンド・フラッツの大いなる賭けは全て吉と出たのだ。